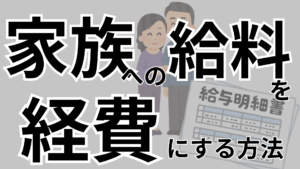不動産を所有していると、賃料や礼金などさまざまな収入が発生します。
これらの収入は原則として 「不動産所得」 に該当し、確定申告が必要です。
しかし、すべての入金がそのまま収入になるわけではなく、保証金や敷金のように一時的に預かるものは収入にならないケースもあります。
本記事では、不動産所得として計上すべき収入の種類やその他の注意点について解説します。
不動産所得の収入になるものとは
毎月受け取るもの
賃借人から毎月受け取る↓のような収入は不動産所得として申告する必要があります。
- 賃料・共益費(貸家、貸店舗、アパート、マンション、貸地、駐車場など)
- 共用部分の電気代・水道代(賃借人から受け取るもの)
- 自動販売機の収入
- NTTからの電柱敷地料
契約開始時に受け取るもの
礼金、権利金
契約開始時に受け取る礼金や権利金についても収入として申告する必要があります。
賃料とは区分して集計する必要がありますので、契約開始時の初期費用の明細などを見て確認しましょう。
保証金、敷金は原則、収入にならない
契約開始時にうけとる保証金や敷金は、退去時に返還が必要なものなので収入ではありません。
退去時には返還するものなので、誰からいくら預かっているか、把握しておくようにしましょう。
ただし、契約開始時に返還しないことが確定しているものについては契約時に収入として計上する必要があります。
契約書の保証金・敷金の取り扱いをよく確認しましょう。
更新時に受け取るもの
賃貸借契約の更新時に受け取る 更新料 も、不動産所得として申告が必要です。
退去時に受け取るもの
退去したときに入居者から受領する原状回復工事の負担金は不動産所得として申告が必要です。
受領せずに、敷金の返金と相殺することがありますので、不動産管理会社からの明細をよく確認しましょう。
不動産収入を計算するうえでの注意点
未収でも収入になる

家賃を滞納している人がいます。
この場合、収入として計上する必要はありますか?
→滞納している状態でも収入として申告が必要です!
家賃を滞納している場合でも、賃貸借契約が継続している限り未収の家賃を収入として計上する必要があります。
共有名義の賃貸物件の場合




賃貸物件について、子どもと50%ずつの共有となっています。
賃料はわたしの口座に100%入金されています。この場合、収入はどのように計上すべきでしょうか?
→収入は持分割合で分けて申告する必要があります。
例えば、持分が50%ずつであれば、それぞれ50%ずつの金額を計上し、両者が確定申告を行う必要があります。
遺産分割協議が確定していない場合
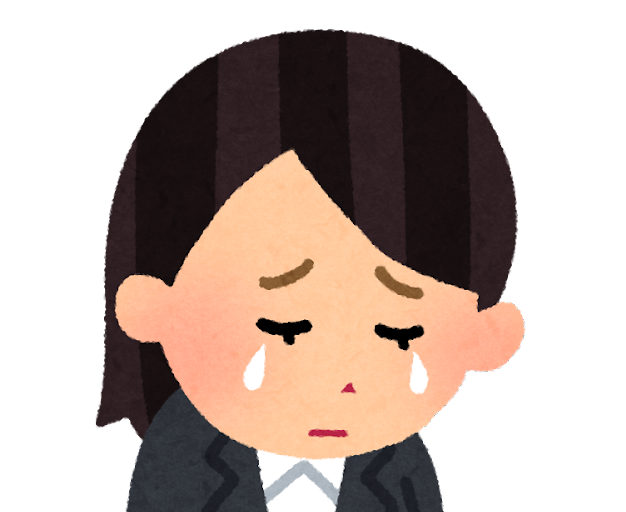
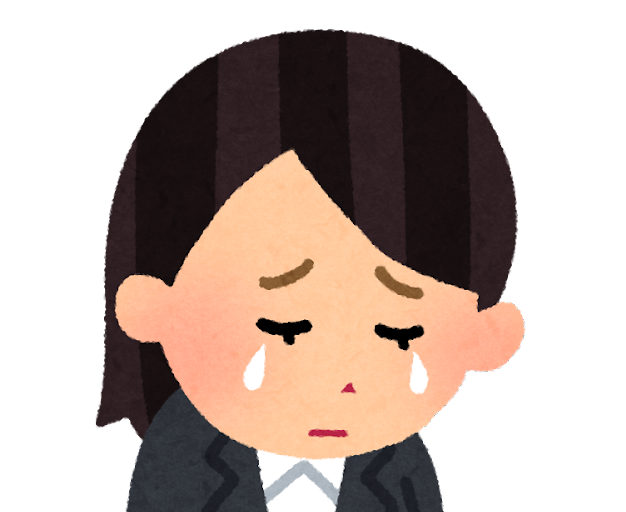
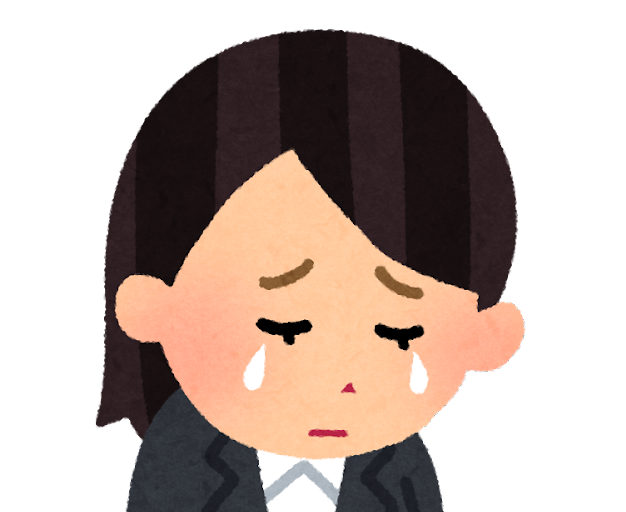
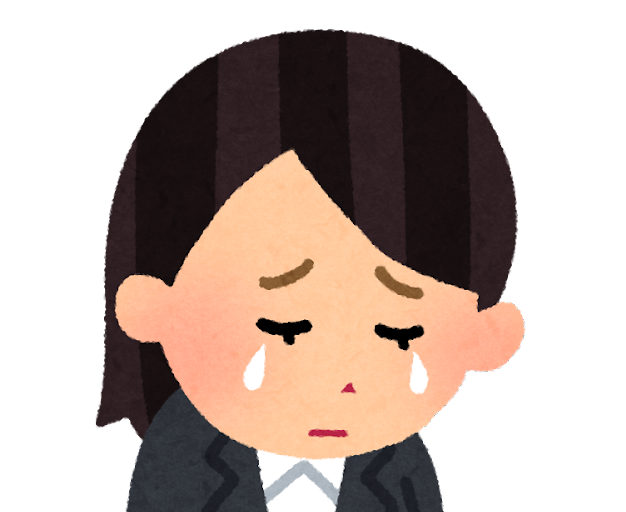
賃貸物件を相続したのですが、子ども3人で遺産分割協議でモメていて賃貸物件の取得者が決まっていません。
賃料は長男名義の口座に入金されている状態です。この場合、収入はどのように計上すべきでしょうか?
→遺産分割が確定するまでは、相続人全員で相続分に応じて収入・経費を計上する必要があります。
たとえば、相続人が3人であれば、各自 1/3ずつの金額を申告し、それぞれ確定申告を行う必要があります。
まとめ
不動産所得として計上すべき収入の種類についてお話しました。
不動産所得として申告が必要な収入には、毎月の賃料だけでなく、契約時の礼金や更新料、未収の家賃なども含まれます。
一方、保証金や敷金は原則として収入になりませんが、契約内容によっては申告が必要になる場合もあります。
正しく所得を計上し、適切に確定申告を行いましょう。
ともの税理士事務所からのお知らせ
当事務所では相続税対策、不動産税務についての有料での個別相談を承っております。
| コース名 | 料金(消費税10%込) |
| 40分コース | 27,500円 |
| 90分コース | 46,200円 |
| 180分コース | 83,600円 |
初回から相談料をいただくかわりに、お客様のお悩みに正面から向き合いオーダーメイドでアドバイスを提供します。
(相談後、他のサービスをご契約いただいた場合には、当該サービスの報酬から相談料を値引きしております。)
現在のご状況や困っていることなど可能な限り詳細にご記載をいただくと適切なアドバイスが可能です。
困っていることがわからない、、、という方でも対応可能ですのでご安心ください。
その際にはお話を聞かせていただきながら問題点の整理を手伝います。
ご興味がある方はこちらからお問い合わせください。
当事務所で提供できるサービスはこちら↓