-

第7回個別相談会を開催しました
-



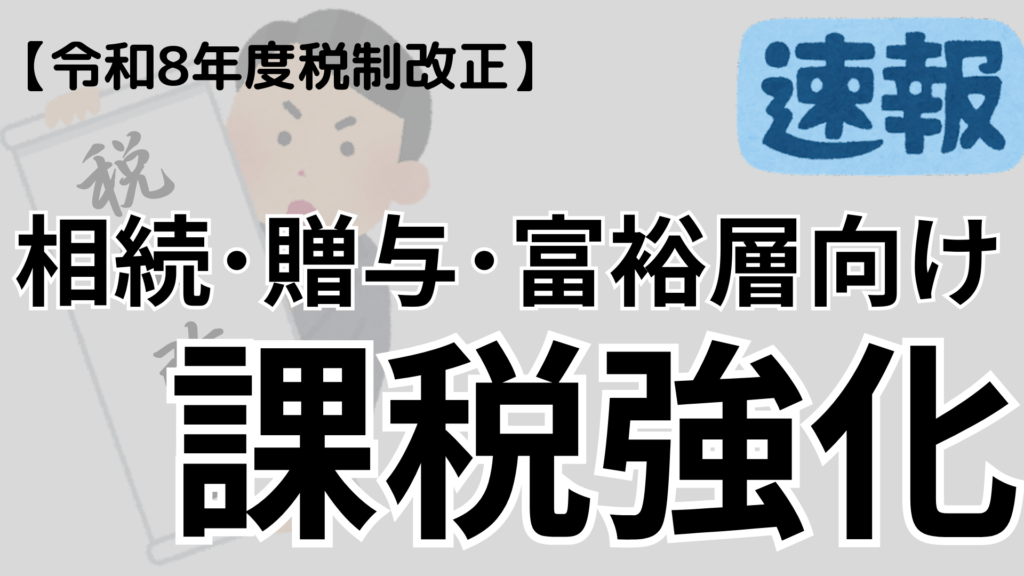
速報版・令和8年度税制改正 相続・贈与・富裕層向けへの課税強化へ!
-




第6回相続個別相談会を開催しました
-



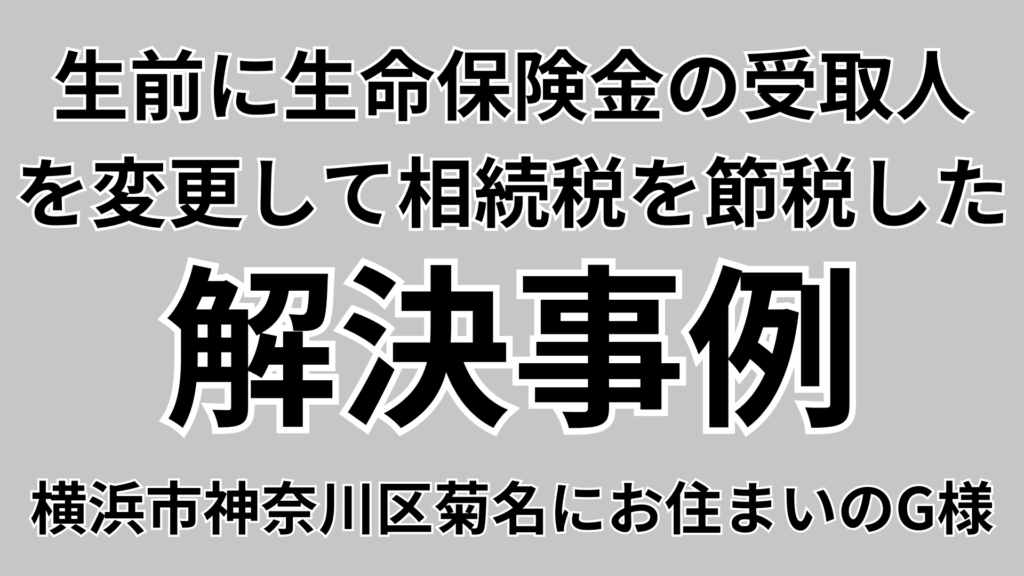
【横浜市港北区菊名の解決事例】生命保険金の受取人を変更で二次相続税を節税
-



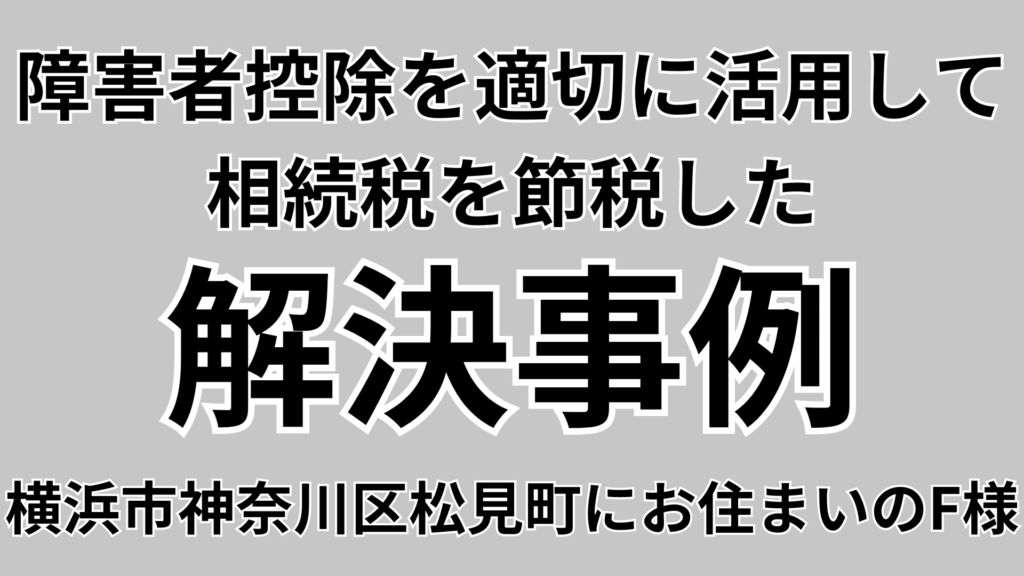
【横浜市神奈川区松見町の解決事例】障がい者控除を適切に活用した節税のご相談
-



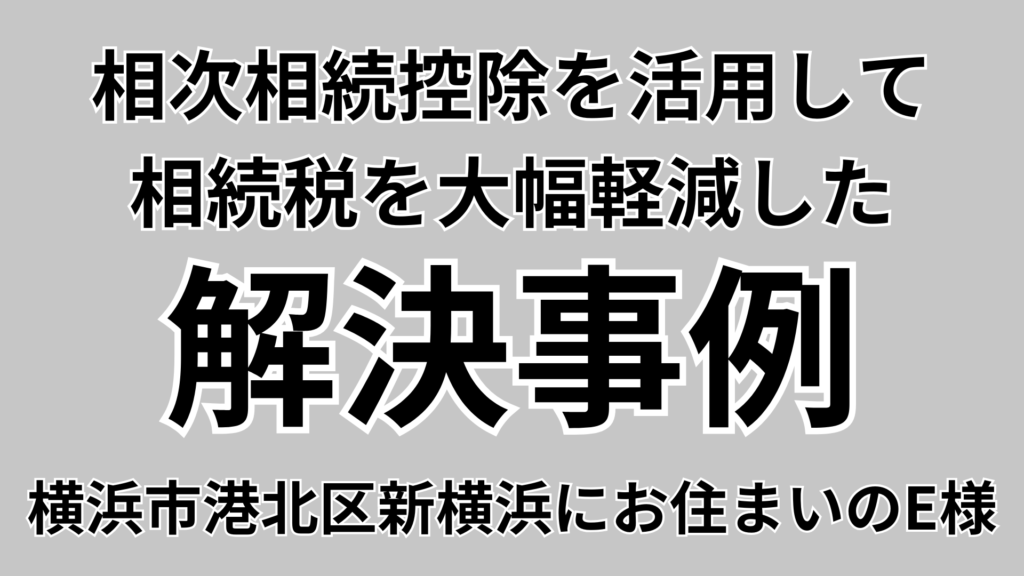
【横浜市港北区新横浜の解決事例】相次相続控除の活用により税額を軽減できた事例
-



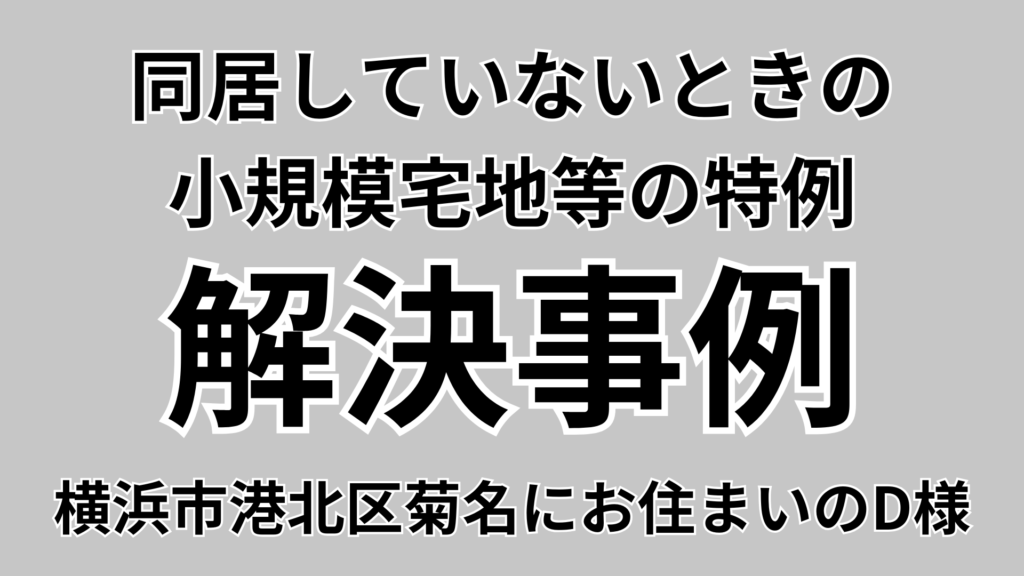
【横浜市港北区菊名の解決事例】同居していない相続人の小規模宅地等特例のご相談
-




【横浜市港北区菊名の解決事例】広い土地の相続税評価の減額のご相談
-




【横浜市港北区菊名の解決事例】空き家特例を活用するための遺産相続のご相談
-




第5回相続個別相談会を開催しました。
-




横浜市港北区菊名にお住まいのA様の相続税申告解決事例
-




神奈川県広告美術協会青年部様でセミナー講師をつとめました
-




自宅を賃貸にしたときの減価償却はどうなる?計算方法を解説!
-




不動産賃貸業の減価償却とは? 基本の仕組みと計算方法を解説!
-




不動産所得の収入とは?計上が必要な収入とその注意点
-




第4回相続個別相談会を実施しました。
-



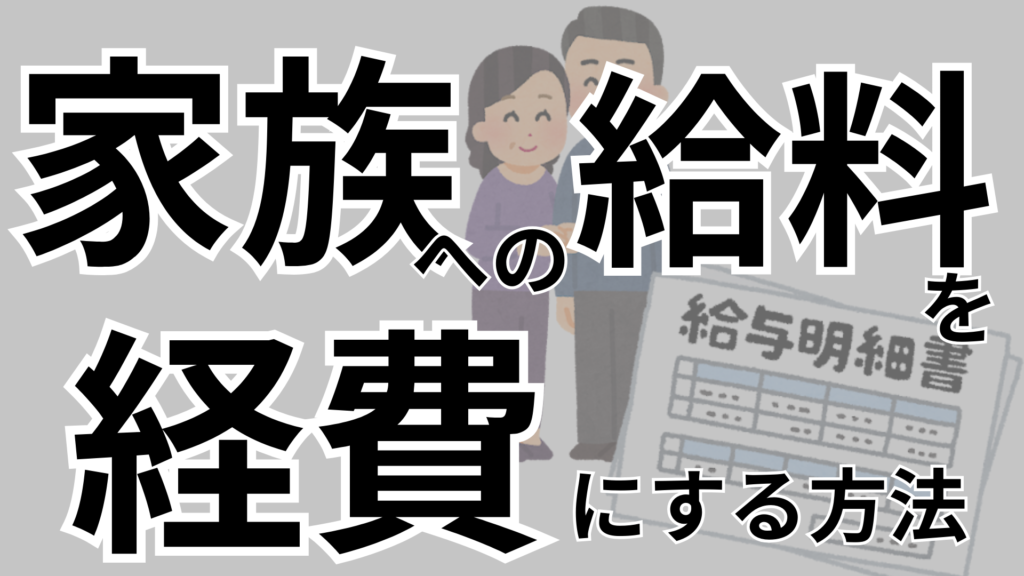
家族に給与を払いたい!青色事業専従者給与の手続きのしかた
-




当事務所ホームページが紹介されました
-




【不動産オーナー必見】不動産所得の必要経費とは?具体例を解説!
-




不動産収入の税負担を減らす!資産管理会社の仕組みとポイント
-



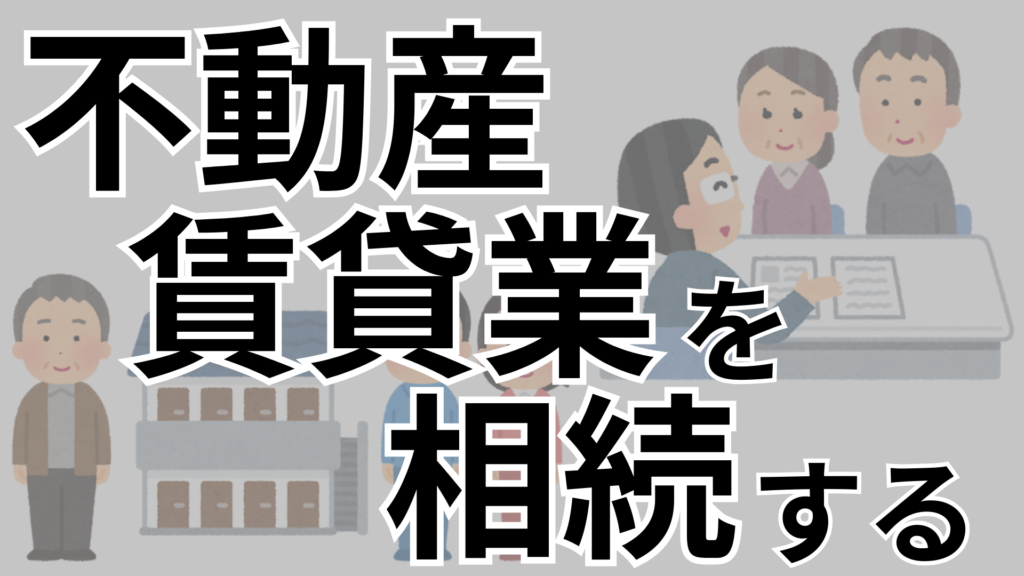
不動産賃貸業を相続したらやるべき3つの手続きと注意点
-



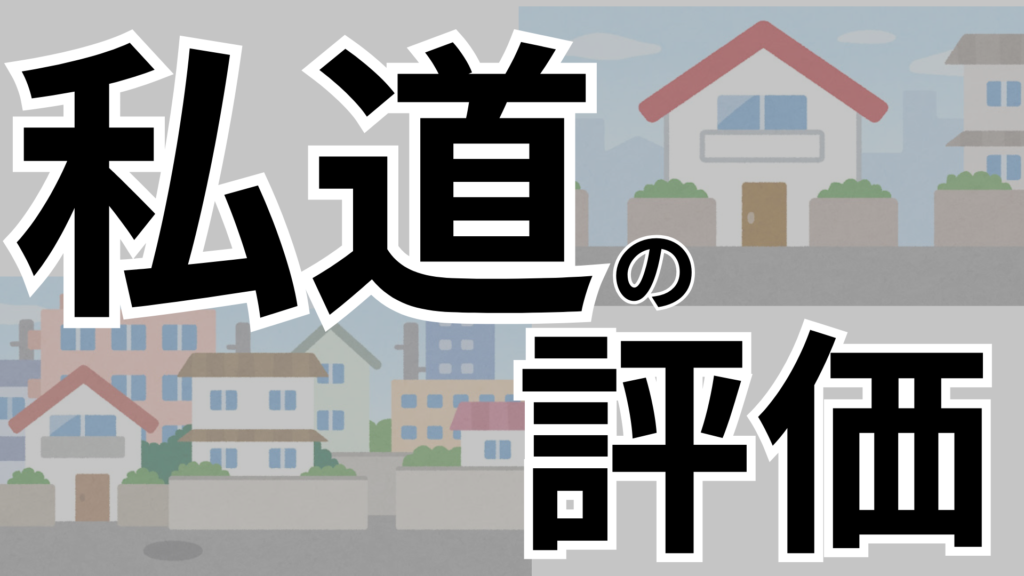
知っておきたい私道の評価方法と減額ポイント
-



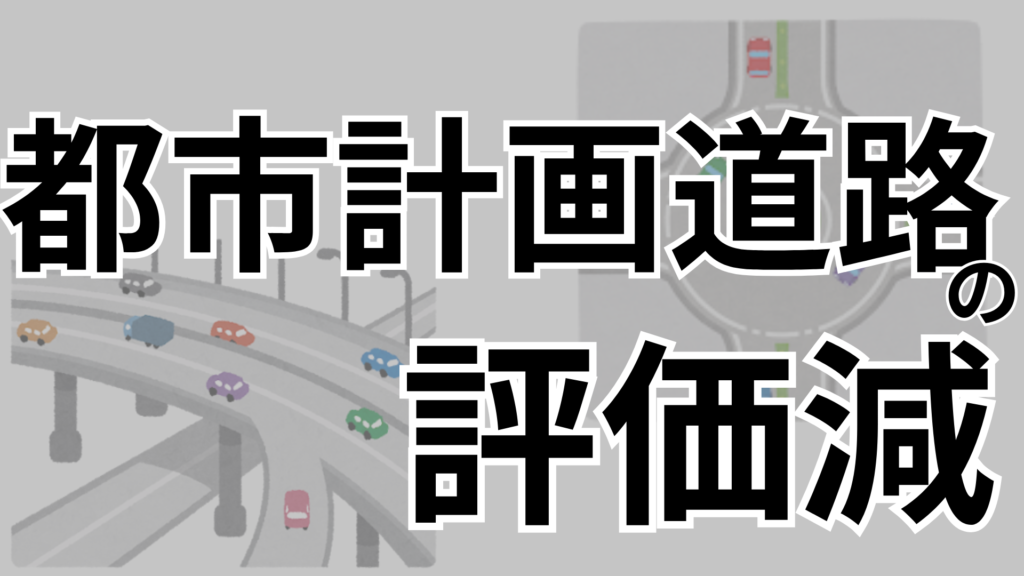
都市計画道路予定地の評価減:確認方法と減額のポイントについて解説!
-



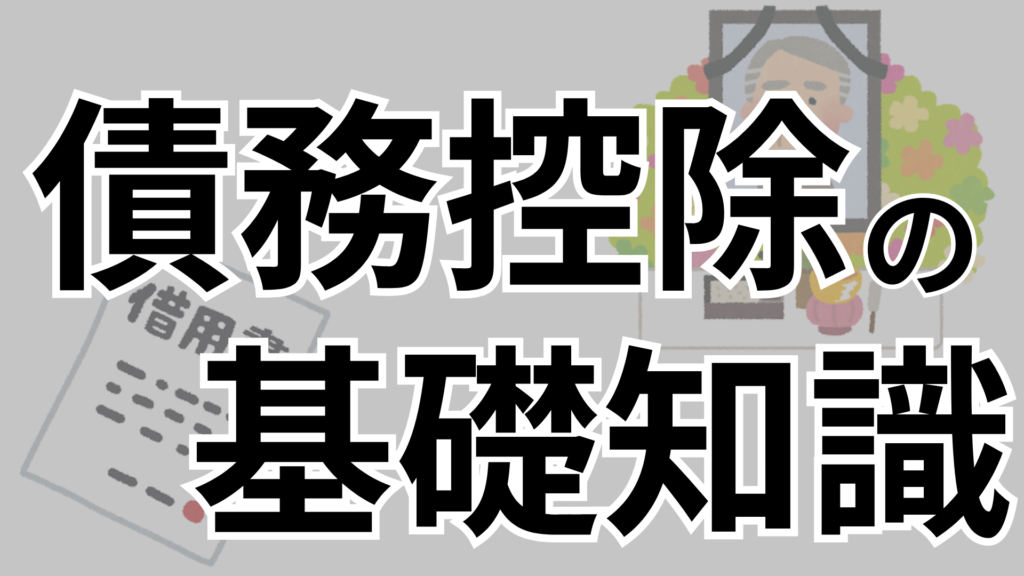
相続税における債務控除の基礎知識と適用範囲について解説!
新着記事
-


当事務所ホームページが紹介されました
当事務所ホームページが「税理士コラボネット」様に、おすすめの税理士事務所として紹介されました。 『プロが選ぶ』横浜市の税理士事務所12選【2025年版】おすすめの会計事務所 | 税理士コラボネット もしよければご覧ください。 税理士コラボネット様、こ... -


【不動産オーナー必見】不動産所得の必要経費とは?具体例を解説!
不動産所得を正しく計算するには、「必要経費」の理解が不可欠です。 必要経費とは不動産収入を得るために直接かかった費用のこと。適切に計上することで税負担を軽減することができます。 今回は不動産所得の必要経費について、具体例を交えながら詳しく解... -


不動産収入の税負担を減らす!資産管理会社の仕組みとポイント
不動産を所有していると、所得税や相続税の負担が気になりますよね。 特に、不動産所得が大きくなると所得税率が高くなり税負担が重くのしかかります…。 そこで検討したいのが、「資産管理会社」の設立です。 不動産収入を会社に移すことで、税負担を軽減... -

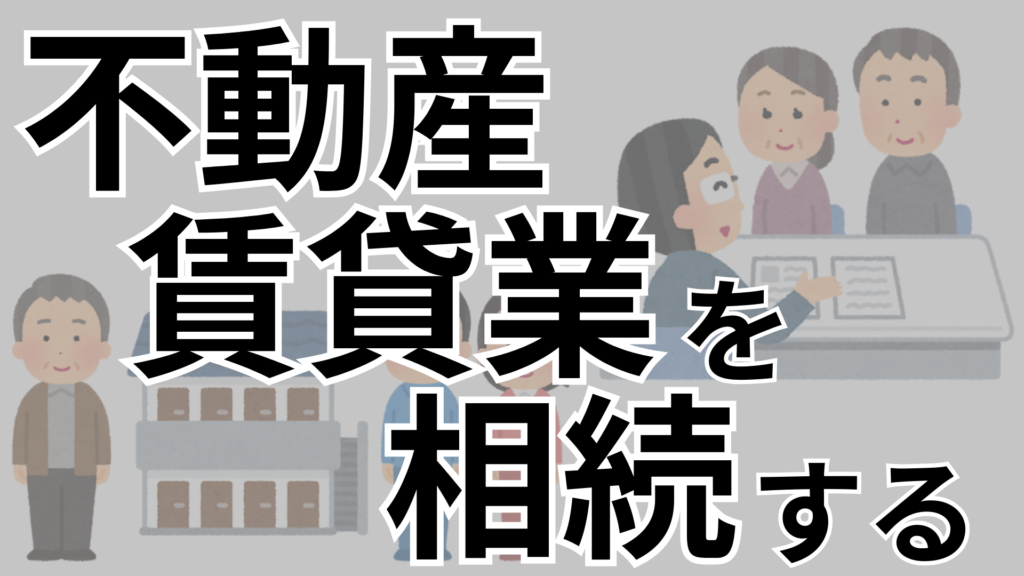
不動産賃貸業を相続したらやるべき3つの手続きと注意点
親や家族が営んでいた不動産賃貸業を相続したとき、何から手をつければいいのか分からず戸惑っていませんか? 青色申告や準確定申告、消費税の手続きなど、やるべきことが多く、期限も決まっているためスムーズな対応が求められます。 この記事では、不動... -

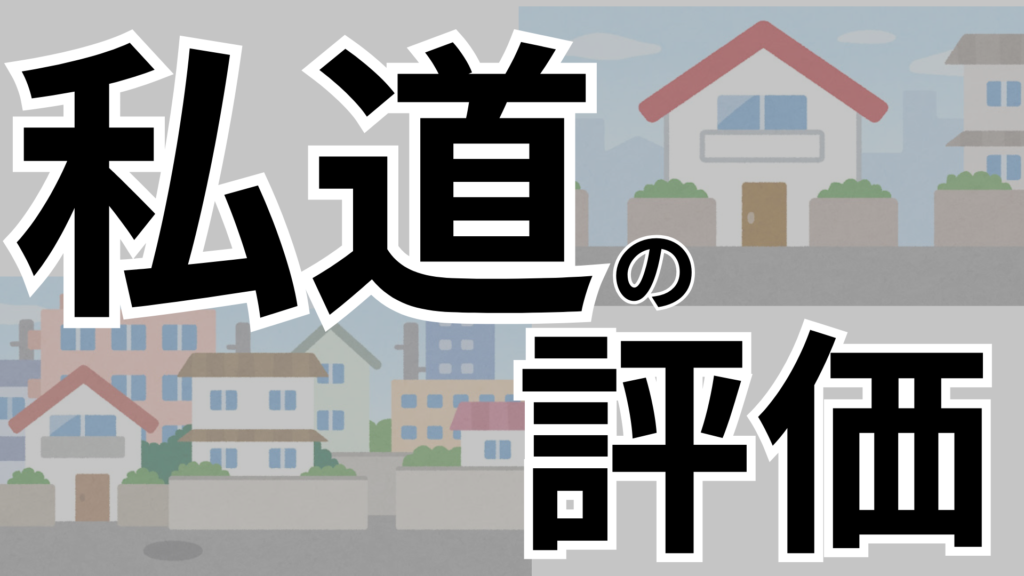
知っておきたい私道の評価方法と減額ポイント
自宅の前の私道を所有しています。私道部分も相続財産の一部になるのでしょうか? 自宅の前にある私道を所有している場合、相続の際にどのように扱われるのか気になる方も多いのではないでしょうか? 私道も個人の財産であるため、相続財産として評価が必要... -

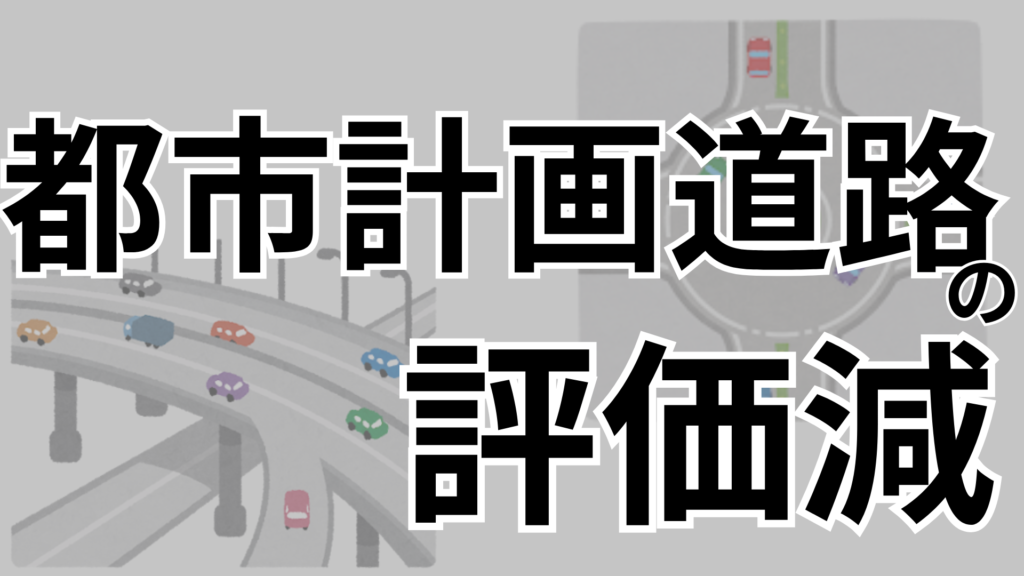
都市計画道路予定地の評価減:確認方法と減額のポイントについて解説!
都市計画道路予定地となっている土地は、評価額を減額できる可能性があります。 これは、将来的に道路整備が予定されているため、土地利用や建築行為に一定の制限があるからです。 本記事では、都市計画道路予定地の評価減の仕組みや適用条件、具体的な計... -

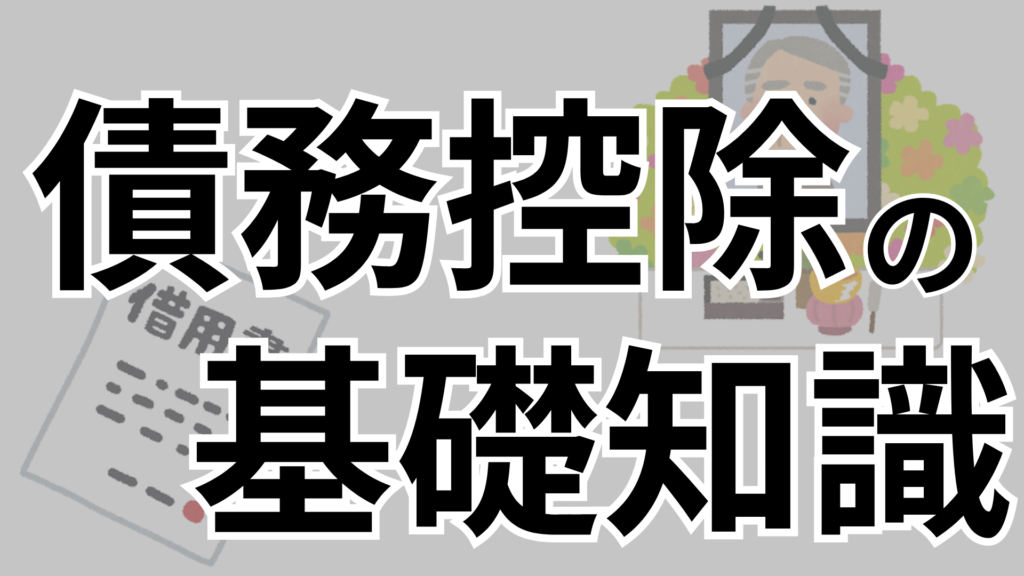
相続税における債務控除の基礎知識と適用範囲について解説!
相続が発生すると、相続人や包括受遺者は被相続人の財産だけでなく、債務(借金や未払いの税金など)も引き継ぐ義務があります。 相続税は、財産の総額(プラスの財産)から債務や葬式費用などを差し引いた「正味財産額」に対して課税されます。 そのため... -

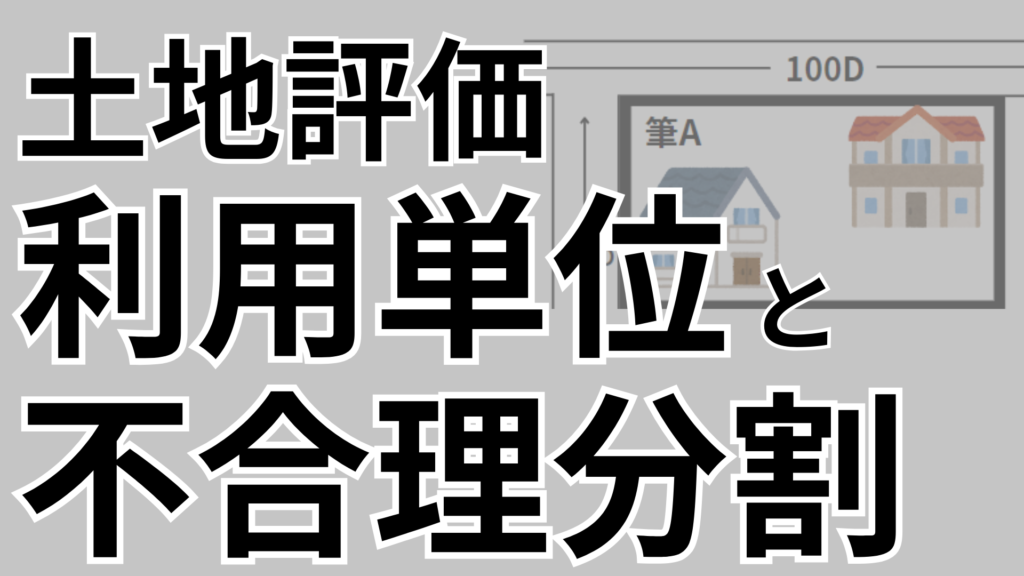
【土地評価のポイント解説】利用単位と不合理分割の注意点
我が家の土地は2つの筆にわかれていて北側と西側が路線価に接しています。 この場合、筆Aと筆Bは別々に評価するのでしょうか?それとも一体で評価するのでしょうか。 土地の相続や評価を考える際に、「評価単位」をどのように区切るかは、相続税額や節税対策... -

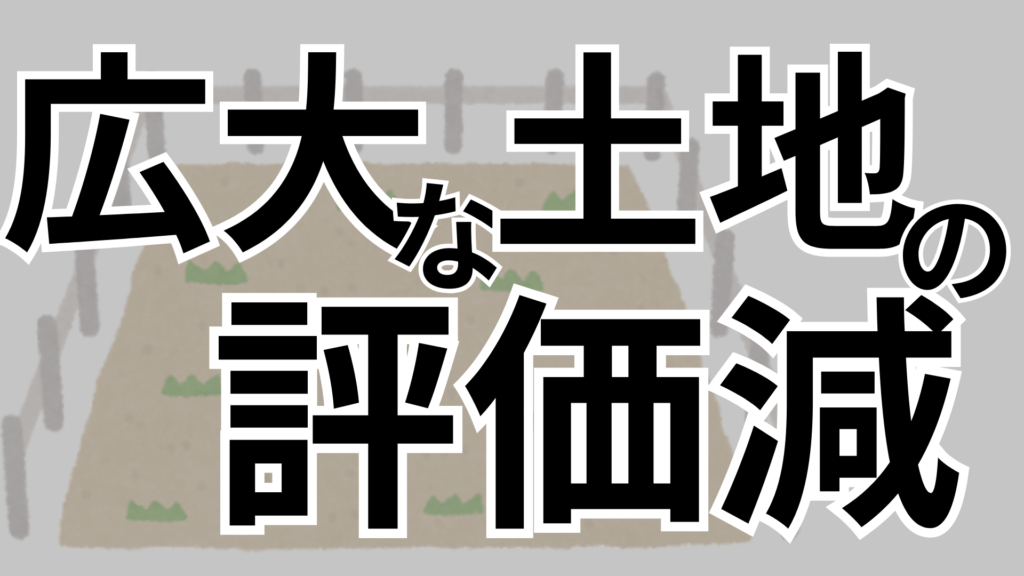
評価減で節税!地積規模の大きな宅地について解説!
広大な宅地を所有する場合、固定資産税や相続税の負担が非常に大きくなりがちです。 しかし、「地積規模の大きな宅地」に該当すれば、評価額を減額できる特例が適用され、負担を軽減することが可能です。 今回は、この制度の概要や適用条件、計算方法をわ... -

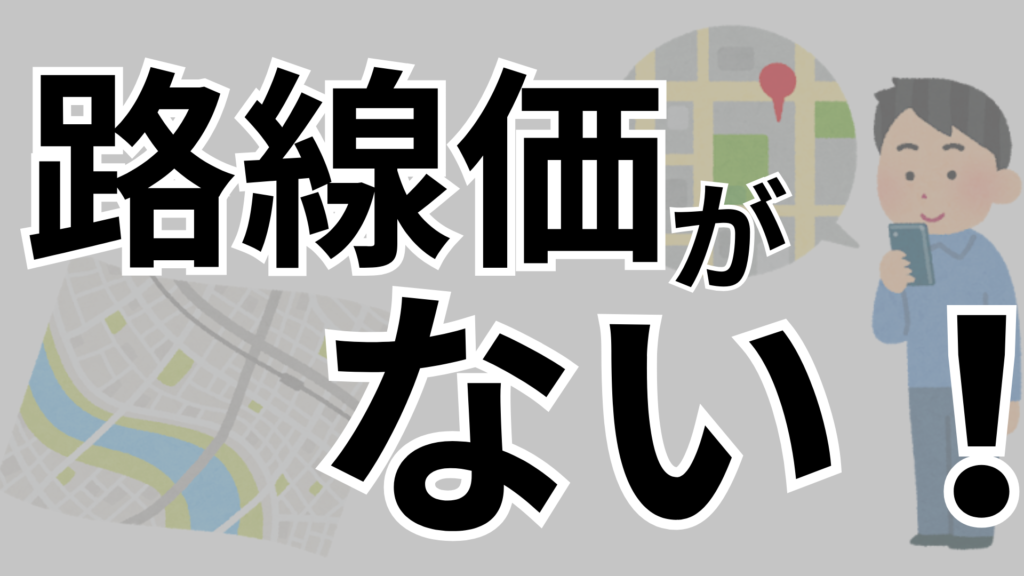
路線価のない土地の評価:特定路線価申請の流れとチェックポイント
相続税の申告、特に土地の評価額に悩んでいませんか? 特に、路線価が設定されていない土地の評価額は、通常の土地と比べて少し複雑です。 相続税の評価額を算定する際、路線価が基準となることが多いですが、すべての道路に路線価が設定されているわけで... -

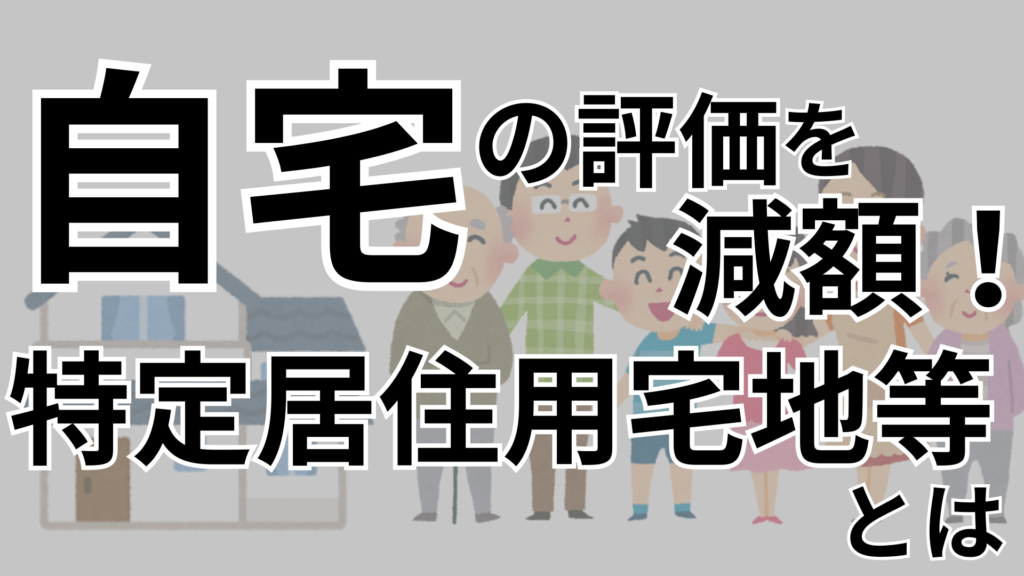
自宅土地は減額できる!特定居住用宅地等について解説!
相続税の節税につながる「小規模宅地等の特例」——その中でも注目したいのが「特定居住用宅地等」です。 相続が発生した際、被相続人の自宅の土地については、一定の要件を満たせば評価額を大幅に減額できる制度があります。 それが「小規模宅地等の特例」... -

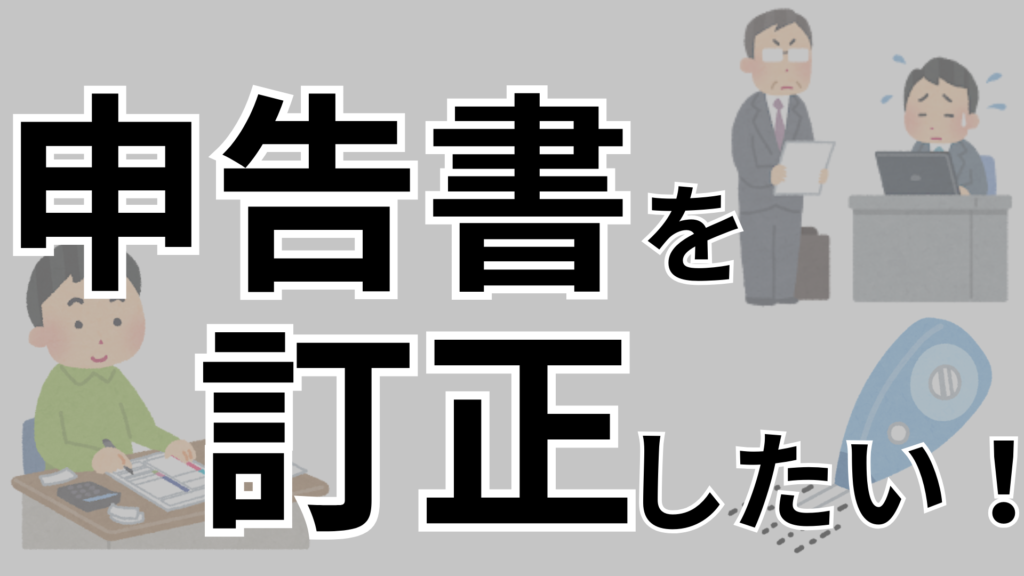
提出した申告書を訂正するときの手続きについて解説します!
相続税の申告書を提出した後で、追加の財産が出てきてしまいました、、、どうすればよいでしょうか? 申告を終えて一安心したのも束の間、新たな財産が判明したり、計算ミスに気づいたりすることは意外とよくある話です。 このような場合、申告内容の訂正手続...
